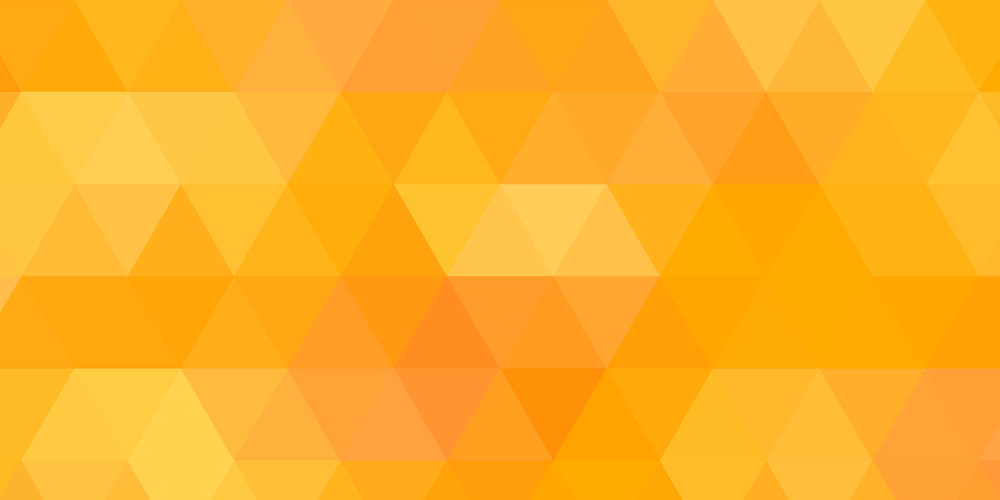フラワーギフト市場の最新動向と分析

はじめに
人の心を癒し、祝福や感謝を伝える象徴として古くから重宝されてきたフラワーギフト。特にパンデミックを経て、人と人とのつながりを大切にする気運が高まったこともあり、その存在感は一層高まりました。デジタル時代においても「リアルな花」を贈るという行為は、今なお強い感情的価値を持ち、需要が絶えません。
本記事では、そんなフラワーギフト市場が今どのような転換期を迎えているのか、オンライン化、サステナビリティ、物流の課題など、多角的な視点で現状と未来を読み解きます。
フラワーギフト市場の現状
2023年、国内の花き小売市場は9,738億円と推計され、前年とほぼ横ばいの推移となりました。これは、コロナ禍による一時的な需要増から落ち着いた形ではありますが、一定の市場規模が安定的に存在していることを示しています。
「2023年の国内花き小売市場規模は9,738億円と推計され、前年とほぼ同水準となった」
引用元:矢野経済研究所
一方、グローバル市場の成長は著しく、2023年に617億1,000万ドル(約9兆円)規模となり、今後10年で800億ドル超までの成長が見込まれています。
「2023年の世界のフラワーギフト市場は約617億1,000万米ドルに達し、2032年には800億米ドルに成長すると予測されている」
引用元:Wise Guy Reports
特に中国・東南アジア・中東などでは中産階級の拡大と文化的受容の進展により、花を贈る習慣が定着しつつあります。
消費者行動の変化と新たなトレンド
オンライン需要の急伸と「非対面ギフト」の台頭
コロナ禍を契機に、花屋のデジタルシフトが加速しました。特に中小規模のフラワーショップが「自社EC」「LINE予約」「SNS販売」などに挑戦し、デジタルでの顧客接点を築いてきたことは大きな変化です。
さらに、ギフト配送の非対面化は贈答文化に新たな価値をもたらしました。
「母の日にオンラインでフラワーギフトを注文しました。直接会えない状況でも、感謝の気持ちを伝えられて良かったです」
引用元:note(MPSジャパン)
このように、直接会うことが難しい状況下でも心を伝える手段として、花は再び脚光を浴びているのです。
サブスクリプション型ギフト:日常に花を取り戻す試み
サブスクサービスは、花の「日常消費」への回帰を促進しています。以前は特別な贈り物としての側面が強かった花ですが、最近は「毎月新鮮なブーケが届く」というサービス形態によって、ライフスタイルアイテムへと変化しています。
「毎月届くフラワーサブスクリプションを利用しています。自宅が華やかになり、生活に彩りが増しました」
引用元:note(MPSジャパン)
この傾向は特に20代~30代の都市部女性に人気で、InstagramやTikTokなどを介して視覚的に“映える”インテリアアイテムとしての花の価値が再評価されています。
価格帯と需要の二極化
市場調査によると、ギフト用花の購入価格帯は3,000~5,000円が45%と最も多く、中価格帯に人気が集中しています。一方で、「カジュアルギフト」として1,000〜1,500円前後のプチギフトも需要が拡大しており、シーンによって予算を柔軟に使い分ける傾向が見られます。
自宅用花の購入頻度は減少傾向にあり、「年3回以上購入する人は17%」にとどまっています。
「2023年の花の購入率は39%。購入価格帯は3,000~5,000円が最多。自宅用は年3回以上の購入者が17%」
引用元:note(MPSジャパン)
また、「日常の贅沢」としての自宅用需要はやや後退傾向にありますが、その分“目的買い”の花の価値は相対的に上がってきています。
環境配慮型ギフトとエシカル消費の拡大
花の美しさだけでなく、その背景にある栽培・流通・包装のサステナビリティが今、消費者の購買動機に深く関わっています。
オランダやケニアでは、CO2削減や公正労働を意識した花の栽培が行われ、日本市場にもそうした**「エシカルフラワー」**が徐々に浸透。MPS(持続可能な花き生産)認証を取得した輸入花を扱うショップも増えています。
「環境意識の高まりは今後の市場を左右する要因の一つ」
引用元:矢野経済研究所
特にZ世代やミレニアル層は「価格」よりも「背景」に共感して選ぶ傾向が強く、ギフトでもその傾向は顕著です。
業界課題:物流と流通のボトルネック
2024年問題として知られるトラック運転手の労働時間制限により、花き業界にも大きな影響が見込まれています。花は生鮮品であるため、輸送スピード・鮮度保持のための冷蔵設備が不可欠です。
この問題に対し、業界では以下の取り組みが進められています:
- 物流容器の規格統一
- 市場連携による共同配送
- 再配達削減のための置き配・時間帯指定配送の導入
「物流の2024年問題により、花き流通も輸送効率化が急務とされている」
引用元:矢野経済研究所
特にフラワーギフトの「鮮度=価値」である点を踏まえ、物流の最適化は今後の競争力を左右する要素になります。
今後の展望と成功戦略
個別化・体験価値・環境配慮がカギ
今後のフラワーギフト市場を制するのは、以下の3軸を柔軟に取り入れたブランドといえるでしょう。
- パーソナライズの強化
手書きメッセージ、名前入りタグ、好みに合わせたブーケ構成など「贈る人・贈られる人」の体験を設計すること。 - オンラインサービスの充実
ギフト設定、配送日指定、AR試し飾り機能など、テクノロジーとの融合も重要な差別化要素。 - エシカル意識の内包
生産背景を開示し、ストーリーあるギフトとして提案することで、感情価値を高める。
「花を贈る」という文化的行為に、デジタルとサステナビリティの文脈を重ねる時代が始まっています。
まとめ
フラワーギフト市場は現在、「贈る意味」「花の物語」「生活との融合」など、単なるモノとしてではなく体験価値としての進化が求められています。
今後は、オンライン販路の強化、ローカルフローリストのDX支援、サステナブルな商品設計など、業界全体での革新が必要です。
時代のニーズを読み解き、柔軟に対応できるプレイヤーこそが、次の市場をリードするでしょう。
Q&A:
-
フラワーギフトのオンライン購入のメリットは?
-
24時間いつでも注文でき、豊富なデザインや価格帯から選べます。遠方の相手にも感謝や祝福の気持ちを簡単に届けられる点も利便性が高いです。
-
サブスクリプションサービスとは?
-
月に一度、または隔週で自宅に新鮮な花が届く定額制のサービスです。日常の中に自然な彩りを加えたい人や、花のある生活を手軽に楽しみたい人に人気です。
-
環境配慮型のフラワーギフトとは?
-
サステナブルな農法で育てられた花や、再生可能・リサイクル可能なパッケージを使用したギフト。地球環境に優しく、エシカル志向の消費者から高い支持を受けています。