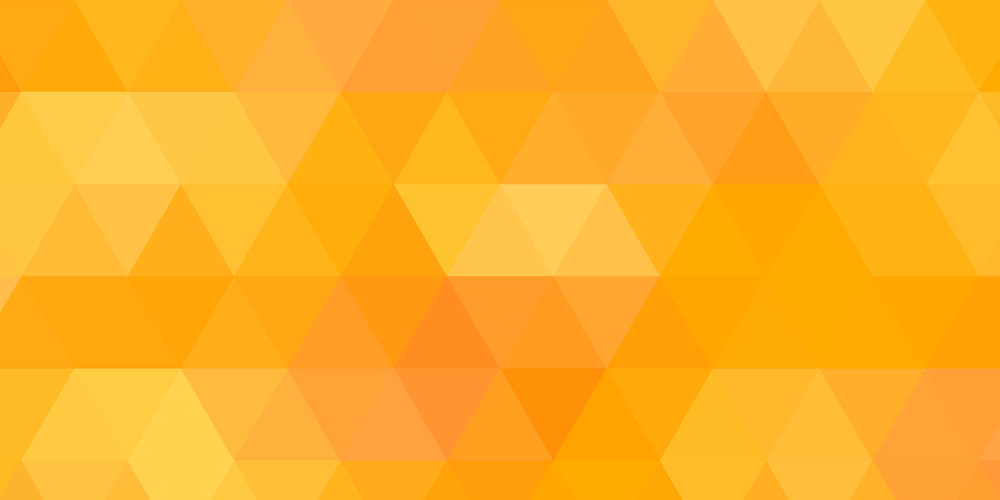冠婚葬祭業界における最新の生花市場動向
はじめに
冠婚葬祭業界における生花市場は、社会変化や消費者ニーズの多様化により大きな転換期を迎えています。結婚式や葬儀といった人生の重要な節目において、生花は感情や敬意を表現する重要な要素として長く親しまれてきましたが、少子高齢化や価値観の変化に伴い、その需要や使われ方も変化しています。


本記事では、最新の市場データや専門家の見解、業界関係者の声を基に、冠婚葬祭業界における生花市場の現状と今後の展望について詳しく解説します。花屋として今後のビジネス戦略を考える上で重要な情報をお届けします。
生花市場の現状分析と変化
市場規模の推移と現状
日本の生花産業は、1998年の約6,300億円をピークに減少傾向が続いています。農林水産省の花き振興施策によると、花き産業は重要な地域経済の担い手であるものの、消費の減少傾向が指摘されています。この背景には、少子高齢化による冠婚葬祭イベントの減少、生活様式の変化、そして消費者の節約志向があります。
特に注目すべきは、コロナ禍からの回復傾向です。農林水産省の花き生産動態調査によれば、緊急事態宣言下では大幅に落ち込んだ花き需要も、徐々に回復の兆しを見せています。
仕入れ価格と流通の変化
生花の仕入れ価格は、気候変動や国際情勢の影響を受けて変動しています。日本花き振興協議会の活動報告では、気候変動や燃油高騰などが、花き生産におけるコスト増加要因として指摘されています。
一方で、流通チャネルの多様化も進んでいます。従来の市場流通に加え、産地直送や海外からの直接輸入など、中間マージンを削減する新たな仕入れ方法が広がっています。
消費者ニーズの変化
冠婚葬祭における花の選択基準も大きく変化しています。従来の「豪華さ」や「伝統」を重視する価値観から、「オリジナリティ」「ストーリー性」「環境への配慮」を重視する傾向が強まっています。矢野経済研究所が発表した「ブライダル市場に関する調査結果2023」では、消費者の価値観の変化により、冠婚葬祭においても個性的で環境に配慮した花の演出が求められるようになっていることが報告されています。
結婚式における生花トレンドの変遷
ミニマルでサステナブルなスタイルの台頭
近年の結婚式では、大量の花を使った豪華な装飾よりも、厳選された少数の花を効果的に活用するミニマルなスタイルが人気を集めています。リクルートの結婚総研が発表する結婚トレンド情報では、結婚式のスタイルとして「ナチュラル・シンプル」を好む傾向が強まっており、これは装花のスタイルにも反映されています。
パーソナライズされた装花の需要
結婚式の個性化が進む中、カップルのストーリーや趣味を反映したオーダーメイドの装花需要が高まっています。「二人の出会いの場所に咲いていた花を中心にアレンジする」「趣味を象徴する植物を取り入れる」など、思い出や個性を表現する依頼が増加しています。
株式会社リクルートの婚礼関連調査では、自分たちらしさを重視するカップルが増加しており、それは装花の選択にも表れていることが報告されています。
国産・地元産の花材の人気
「フードマイレージ」ならぬ「フラワーマイレージ」の概念が広まり、環境負荷の少ない国産や地元産の花材を選ぶカップルが増えています。特に、地元の花農家と直接提携し、季節の花を活用した「ローカルフラワー」のウェディングが注目を集めています。
日本花き振興協議会の活動報告では、国産花きの需要拡大に向けた取り組みが進められており、結婚式での国産花材活用も推進されています。
葬儀様式の変化と生花需要への影響
小規模化する葬儀と生花需要
葬儀の小規模化・簡素化傾向は依然として強く、これが生花需要に大きな影響を与えています。鎌倉新書の「葬儀に関する調査2023」によれば、2023年に執り行われた葬儀のうち、家族葬や一日葬などの小規模葬儀が全体の約70%を占め、従来型の一般葬が大きく減少しています。
株式会社日比谷花壇の公式発表によれば、小規模葬儀であっても花への需要は健在で、むしろ一人当たりの花関連支出は増加傾向にあるとされています。少人数だからこそ、一つ一つの花に込められた思いや質が重視される傾向が見られます。
追悼の形の多様化
従来の葬儀に代わる新たな追悼の形も生まれており、それに伴い花の役割も変化しています。「お別れ会」「偲ぶ会」など、故人を偲ぶためのカジュアルな集まりでは、堅苦しい供花よりも、故人の人柄や好みを反映したパーソナルな花の演出が好まれます。
公益社団法人全日本葬祭業協同組合連合会の発表資料では、近年の葬送スタイルの変化と共に、花の使われ方も多様化していることが報告されています。
エンディングノートと事前相談の増加
自分の葬儀について事前に考える「終活」の浸透に伴い、葬儀での花についても事前に希望を残す人が増えています。一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会の調査報告では、終活の一環として葬儀に関する希望を記録する人が増加しており、その中には花に関する希望も含まれています。
この傾向は花屋にとって重要な変化です。葬儀社と連携し、事前相談に対応できる体制を整えることで、新たなビジネスチャンスとなっています。
環境配慮型の取り組みと持続可能な花ビジネス
サステナブルな花材と装飾技術
環境への配慮は、冠婚葬祭業界でも無視できないトレンドとなっています。特に注目されているのが、フローラルフォームと呼ばれる吸水性スポンジの代替品です。従来のフローラルフォームは生分解されにくいため、環境負荷が高いという問題がありました。
一般社団法人日本フラワーデザイナー協会(NFD)では、環境に配慮した花のデザインや技術に関する研究と普及活動を行っており、業界全体のサステナビリティへの意識向上に貢献しています。
フラワーロスへの対応
冠婚葬祭で使用された花の多くが、イベント終了後に廃棄されるという課題に対する取り組みも活発化しています。「フラワーロス」削減に向けた新しいビジネスモデルとして、結婚式で使用した花を再利用して病院や高齢者施設に届ける「フラワーリレー」サービスや、葬儀後の花を使ったワークショップなどが広がっています。
農林水産省の花き振興施策においても、花きの需要拡大と共にフラワーロス削減への取り組みの重要性が強調されています。

認証制度と消費者認知
海外ではすでに「サステナブル・フローリスト認証」などの制度が確立されていますが、日本でも類似の動きが始まっています。
消費者庁の「倫理的消費」調査報告書によれば、環境や社会に配慮した消費行動への関心が高まっており、それは花業界にも波及しています。
デジタル化が進む花業界の最新動向
オンライン注文とバーチャルコンサルテーション
コロナ禍を機に加速した花業界のデジタル化は、冠婚葬祭分野でも定着しつつあります。特に葬儀の供花注文では、オンラインでの24時間受付システムが標準化しています。経済産業省の「令和4年度電子商取引に関する市場調査」によれば、Eコマース市場全体が拡大する中、生花・園芸分野でもオンライン取引が増加傾向にあります。
また、結婚式の装花についても、ビデオ通話を活用したバーチャルコンサルテーションが一般化しています。これにより、地方在住のカップルが都市部の人気フローリストに相談したり、海外在住の親族も打ち合わせに参加したりすることが可能になっています。
SNSマーケティングとポートフォリオの重要性
Instagram、Pinterest、TikTokなどのビジュアル系SNSは、冠婚葬祭花屋の重要なマーケティングツールとなっています。特にInstagramでは、ハッシュタグ「#ウェディングフラワー」の投稿が増加しており、多くのカップルがSNSを通じて花屋を選ぶ傾向が強まっています。
総務省の情報通信白書でも、SNSを活用した中小企業のマーケティング事例として、花業界の取り組みが紹介されています。現代の花屋にとって、デジタル上での美しいポートフォリオ構築は不可欠なスキルとなっています。
AR/VRの活用
最先端の花屋では、拡張現実(AR)や仮想現実(VR)技術を活用したサービスも登場しています。特に大規模な結婚式場やセレモニーホールと提携する花屋では、ARアプリを使って会場装飾のシミュレーションを行うサービスが注目を集めています。
ホテル椿山荘東京のような高級婚礼施設では、デジタル技術を活用した装花提案が行われており、顧客満足度の向上につながっています。
業界関係者の実践事例と成功戦略
専門特化型の花屋の成功事例
市場環境が厳しい中でも成長を続ける花屋には、特定の分野に特化することで差別化を図る戦略が見られます。例えば、株式会社日比谷花壇のように、冠婚葬祭向けの専門サービスを展開することで、安定した需要を確保している企業が見られます。
帝国データバンクの業界動向調査では、花卉小売業の中でも専門特化型の企業が比較的安定した業績を維持していることが報告されています。
セレモニーホールとの戦略的提携
安定した受注を確保するため、セレモニーホールや結婚式場と戦略的な提携関係を構築する花屋も増えています。矢野経済研究所の「2023年版 葬祭市場の展望と戦略」によれば、葬儀の小規模化・簡素化が進む中でも、花に関連した市場については一定の需要が維持されていることが報告されています。業績好調な花店の多くがセレモニー施設との提携を強化していることも指摘されています。
花屋とセレモニー施設の関係性においては、単に安価な花を提供するのではなく、施設のコンセプトに合わせたオリジナルの花デザインを開発し、他社との差別化に貢献することで信頼関係を築いている事例が多く見られます。
多角化と新サービス開発
冠婚葬祭関連の花需要だけでは成長に限界があるとして、関連分野への多角化を進める花屋も目立ちます。例えば、フラワーアレンジメント教室の開設や、プリザーブドフラワーギフト事業、そして企業向けのサブスクリプションサービスなど、新しい収益源の開発が進んでいます。
経済産業省の「特定サービス産業動態統計調査」でも、小売業の中でも定期購入モデルを導入した事業者の収益性が向上していることが指摘されており、花業界でも同様の傾向が見られます。
海外の先進的取り組みと日本市場への示唆
欧米のサステナブルフラワー運動
欧米では「サステナブルフラワー運動」が急速に広がっており、日本の冠婚葬祭業界にも大きな影響を与えつつあります。特に英国の「Flowers From The Farm」は、地元産の季節の花を使ったウェディングを推進するネットワークとして成功しており、日本でも類似の取り組みが始まっています。
ジェトロ(日本貿易振興機構)の海外市場調査レポートでは、欧米を中心に環境に配慮した花き産業のトレンドが紹介されており、日本市場への示唆が示されています。
アジア諸国の葬儀花文化と国際化
シンガポールや台湾などのアジア諸国では、伝統的な葬儀花と西洋スタイルを融合させた新しい供花スタイルが生まれています。
観光庁の訪日外国人消費動向調査では、日本を訪れる外国人の中で、日本の伝統文化や冠婚葬祭に関心を持つ層が一定数存在することが報告されており、花業界にとってもインバウンド需要は無視できない要素となっています。
今後の市場予測と花屋が取るべき戦略
2025年以降の市場予測
矢野経済研究所の「2023年版 葬祭市場の展望と戦略」によれば、冠婚葬祭における生花市場は今後も緩やかな変化が予想されています。特に「小規模葬」や「家族葬」における供花需要や、環境配慮型の花装飾、デジタル技術を活用したサービスの分野は、需要の変化が見込まれています。
また、人口動態の変化により、葬儀関連の花需要は今後も一定の需要が見込まれますが、高齢者の好みや価値観の変化に対応する必要があるとの指摘もあります。
花屋が取るべき戦略的方向性
変化する市場環境の中で花屋が成長するためには、以下の戦略的方向性が重要だと専門家は指摘しています:
- 専門性と差別化の追求: 冠婚葬祭全般ではなく、特定のセグメントに特化し、専門性を高める
- デジタル技術の積極活用: オンライン相談、AR/VRの活用、デジタルマーケティングの強化
- 持続可能性への取り組み: 環境負荷の少ない花材や技術の導入、フラワーロス削減の仕組み構築
- 多角的な収益源の開発: 冠婚葬祭イベント以外の関連サービスや、サブスクリプションモデルの導入
- 人材育成と知識のアップデート: 変化する顧客ニーズや技術トレンドに対応できる人材の育成
中小企業庁の「小規模企業白書」でも、小売業の生き残り戦略として、特化型ビジネスモデルの構築やデジタル技術の活用が重要視されており、花業界でも同様の方向性が示されています。
まとめ
冠婚葬祭業界における生花市場は、少子高齢化や価値観の多様化、デジタル化の波を受けて大きく変化しています。市場全体としては縮小傾向にありますが、専門性の高い分野やサステナブルな取り組み、テクノロジーを活用した新サービスなど、成長可能性のある領域も存在します。
特に注目すべきは、「量」から「質」への転換、「画一的」から「パーソナル」への移行、そして「単発取引」から「継続的関係構築」へというパラダイムシフトです。これらの変化を的確に捉え、顧客の感情や価値観を深く理解した上で、花の持つ本質的な価値を提供できる花屋が、これからの時代に生き残り、成長していくでしょう。
花には人々の感情を伝え、人生の節目を彩る力があります。その本質的な価値は、社会がどれだけ変化しても変わることはありません。変化を恐れず、むしろ変化を新たな機会と捉え、花の持つ力を最大限に活かす方法を常に探求していくことが、冠婚葬祭業界で花を扱う全ての事業者に求められています。
よくある質問
Q1. 生花の需要が減少している主な理由は何ですか?
少子高齢化による冠婚葬祭イベントの総数減少が最も大きな要因です。内閣府の少子化社会対策白書によれば、婚姻件数の減少と葬儀の小規模化が進んでおり、これが花の総需要量に影響しています。また、ライフスタイルの変化により、自宅での花の消費習慣が減少していることも影響しています。一方で、パーソナライズされた高付加価値の花サービスへの需要は増加傾向にあり、市場の二極化が進んでいると言えます。
Q2. 環境に配慮した生花の取り組みにはどのようなものがありますか?
環境配慮型の取り組みとしては、以下のような例が挙げられます:
- 地元産の花を使用する「ローカルフラワー」の推進(輸送による環境負荷の削減)
- 無農薬または減農薬で栽培された花の活用
- 生分解性の花資材(フローラルフォームの代替品など)の使用
- 冠婚葬祭で使用後の花を再利用する「フラワーリレー」プログラム
- 水耕栽培など、環境負荷の少ない栽培方法で育てられた花の活用
- 花の廃棄を減らすための需要予測システムの導入
環境省の「環境にやさしい企業行動調査」でも、花き産業における環境配慮型の取り組みが紹介されています。
Q3. 今後の生花市場の展望はどうなっていますか?
矢野経済研究所の市場調査によれば、全体的な市場規模は緩やかな変化が予想されていますが、高付加価値セグメントでは可能性が見込まれています。特に以下の分野では、需要の変化が予測されています:
- パーソナライズされた花サービス(故人や新郎新婦の個性を反映したデザイン)
- 環境配慮型の花装飾(サステナブルな材料や手法を用いたもの)
- デジタル技術と融合したハイブリッドサービス(ARなどを活用した提案)
また、葬儀関連の花需要は高齢化社会の進行により今後も一定の需要が見込まれますが、従来型の供花から、より個性的で現代的なスタイルへの移行が進むと予測されています。