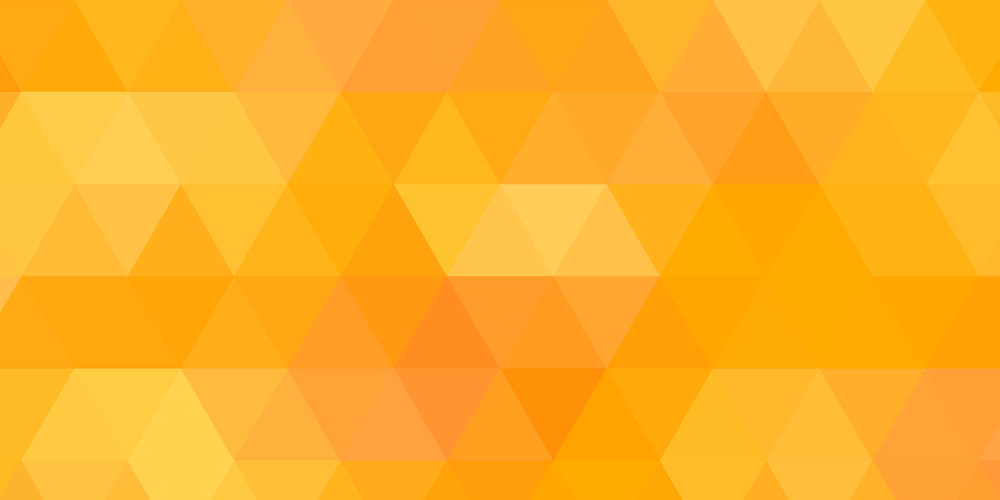葬儀用生花市場の成長性と今後の展望|花屋が押さえておきたい市場の変化
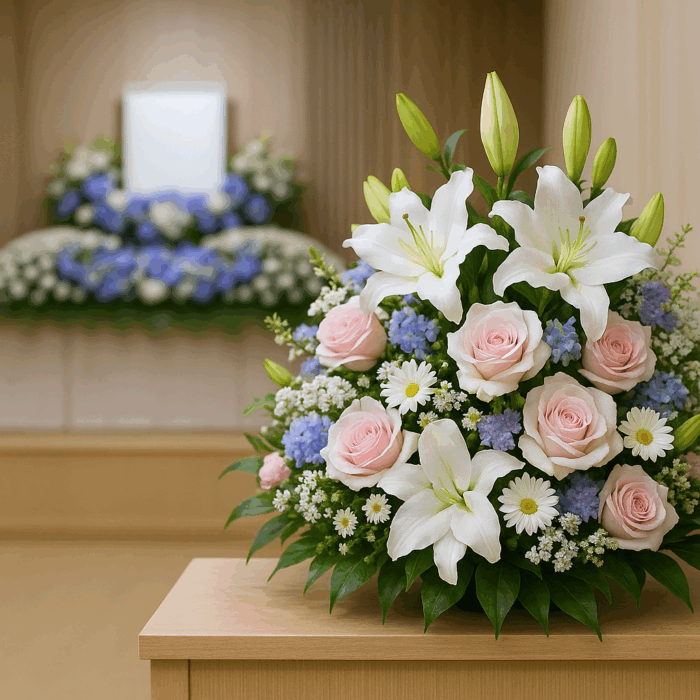
はじめに
高齢化が進む日本社会において、葬儀市場は今後も一定の需要が見込まれる分野です。中でも、葬儀用生花は「形式を整える」だけでなく、「個人や家族の思いを託すもの」へと役割が変わりつつあります。花屋にとっては単なる納品業務ではなく、心を込めた提案と効率的な運営が求められる重要な分野です。
この記事では、葬儀用生花市場の成長性、需要の背景、今後の展望、そして花屋が取るべき戦略について、現場視点で詳しく解説します。
市場の成長背景とデータに見る傾向
高齢化と家族葬の増加
2023年の厚生労働省の統計によれば、日本の死亡者数は過去最高の156万人を超えました(※出典:厚生労働省 人口動態統計)。これに伴い、葬儀件数も増加。特に家族葬の比率が高まり、少人数で行う葬儀において「花で想いを表現する」需要が高まっています。
装花単価の二極化
高級花材や個人の趣味を反映したオーダーメイド型の装花ニーズと、コスト重視の定型プランの二極化が進んでいます。提案の柔軟性とバリエーションが重要になっています。
地域格差と供給体制
地方ではJAや仲卸による流通が強く、都市部ではフラワーデザイナーとの連携による差別化が進んでいます。オンライン受注や配送対応の有無で、業者選定に差が出る時代になりました。
今後の展望と業界の変化
パーソナルな演出の浸透
2020年代以降、特定の花を使った「その人らしさ」を表現する装花が標準化しつつあります。AI画像生成や事例共有アプリの進化により、施主側も装花のイメージを明確に持つようになってきています。
環境配慮とSDGsへの対応
リサイクル花器の使用、プラスチック資材削減、地産地消の花材選定など、環境への配慮も評価ポイントになっています。エコに配慮した花屋としての姿勢が支持される傾向です。
筆耕や備品の一括提案化
名札や案内札、席札などを筆耕ソフト「いちばん」で一括管理できる体制があると、会場側との取引もスムーズです。ワンストップ対応が「選ばれる理由」になるケースが増えています。
花屋が取るべき対応と提案の工夫
- 価格帯別の装花提案(ベーシック/パーソナル/高級)を整備
- 地元JAや市場との連携による安定仕入れ
- 筆耕や納品、設営まで一貫対応できる体制づくり
- 季節感や故人らしさを重視した装花事例の定期更新
まとめ:今こそ準備すべき時期
葬儀用生花市場は、需要が安定しており、提案と運営力で差がつく分野です。今後の成長を見越して、柔軟な対応力・環境意識・ワンストップ提案を整備しておくことで、地域で信頼される花屋としての地位を築けるでしょう。
関連記事のご案内
よくある質問(Q&A)
-
葬儀用生花は今後も需要があるのでしょうか?
-
はい。高齢化の進行とともに安定需要が見込まれます。
特に家族葬や直葬が増える中で、少人数でも「きちんとした花を贈りたい」というニーズは堅調です。
-
今から始めても新規参入できますか?
-
十分可能です。
小ロット・短納期・地域密着型の強みを活かすことで、大手では対応できないニーズを拾うことができます。無償協力などから関係構築するのが有効です。
-
競合との差別化には何が有効ですか?
-
装花のデザイン力+対応力の両立がカギです。
花材の質・センスに加え、「名札・案内札もまとめて手配できる」「LINEやクラウドで写真共有可能」など、運用面の手軽さも強みになります。