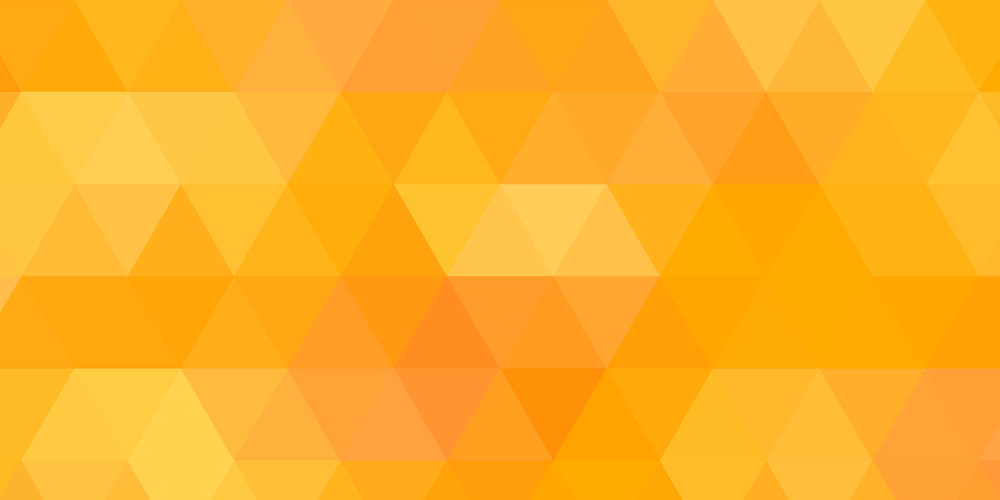葬儀場装花の基本ルール:敬意を表す空間づくりのために知っておきたいこと

はじめに:装花は“弔いの言葉”
葬儀場装花は、言葉を超えて故人と遺族へ想いを届ける「花による祈り」です。
その場にふさわしい装花は、会場全体の雰囲気を整え、厳粛な時間を演出します。
この記事では、葬儀空間での装花における知っておくべき基本的なルールとマナーを解説します。花屋として信頼される第一歩に、ぜひお役立てください。
花材選び:白を基調とした落ち着きのある配色
葬儀場では、白とグリーンを基調にした花材が基本とされています。
白ユリ、菊、カーネーションなどの白花を中心に、グリーン系の葉物を合わせることで、清浄感と品位のある雰囲気が生まれます。
淡いピンクや薄紫などの「色花」を使用する場合もありますが、全体に落ち着いたトーンを保つことが求められます。
宗教や地域慣習にも配慮し、派手すぎず、故人やご遺族の想いに沿った花選びを心がけましょう。
形と配置:空間に調和する左右対称のデザイン
祭壇両脇に対称的に配置された装花(花立て)は、葬儀装飾の基本形です。
人の視線は中央へ集まりやすいため、花が主張しすぎないようバランスを重視した配置が求められます。
供花やお供えの花は、祭壇よりもやや低めに配置するのが原則。
また、会場の広さや天井高に応じて、奥行き・高さを調整することも忘れてはいけません。「控えめで美しい佇まい」が理想的な装花の在り方です。
花の鮮度と保ち方:開式まで持たせる工夫
装花の品質は、「式の時間までどれだけ美しさを保てるか」に左右されます。
- 夏季は特に、吸水スポンジ(オアシス)への十分な給水が重要
- 湿度や気温によっては、ミストスプレーや冷却シートの使用も有効
- 冷暖房の効いた会場内であっても、直射日光や送風の直当てを避ける配置が必要です
事前準備ではなく、当日朝の搬入・設営を原則とし、式中の鮮度保持を第一に考えましょう。
宗教・弔意への配慮:形式に合わせた色使い
日本の葬儀は仏式が主流ですが、神式やキリスト教式では異なる配色もあります。
- 仏式 → 白中心(+淡いピンクや紫)
- 神式 → より簡素に、控えめな白・緑
- キリスト教式 → 白百合中心。黄色・ブルー系を加えることも
「宗派に関わらず落ち着いた花選び」は共通ルールですが、施主の希望を優先する柔軟性も大切です。
導線とサイズ感:見栄えと搬入経路を両立
装花は見た目の美しさだけでなく、搬入経路や設置環境への対応力も求められます。
- 式場によってはエレベーターや入口が狭い
- 搬入ルートの確認は事前に済ませておく
- 会場内の導線(参列者の動き)を妨げないサイズ設計が必要
特に花立やアーチ装飾などの大物は、分割搬入が可能な設計が望まれます。
まとめ:花で送る“敬意”を形にするために
葬儀場装花の基本ルールを押さえることは、現場での信頼獲得にもつながります。
- 色は「白とグリーン」ベースで落ち着きを演出
- 配置は左右対称を基本に、視線を妨げない工夫を
- 鮮度保持・宗教配慮・導線対策を怠らない
こうした配慮が、ただの装飾を「敬意ある表現」へと昇華させます。
花屋として弔いの現場に立ち会うために、技術だけでなく心の準備も忘れずに。
関連記事のご案内
- 🔗 花祭壇デザインの基礎テクニック
※花の種類や配置、空間づくりの視点から花祭壇の基本を学べます。 - 🔗 セレモニー花装飾の基本知識
※供花・式場全体の装飾構成について詳しく解説しています。 - 🔗 花屋が知っておくべき葬儀マナー
※納品・接客・服装など現場マナーも押さえておきたい方へ。
よくある質問(Q&A)
-
色花は避けるべきですか?
-
基本は白系ですが、淡い色を差し色として使う程度であれば問題ありません。施主や宗派の意向に合わせましょう。
-
式場に到着後すぐに花がしおれてしまうのですが?
-
オアシスへの水量が足りているか、冷暖房の影響を受けていないかを確認してください。搬入後の霧吹きも有効です。
-
装花のサイズや高さに決まりはありますか?
-
祭壇より目立たないことが基本です。参列者の目線(約120cm)より高くなりすぎないことを目安にするとバランスが良くなります。