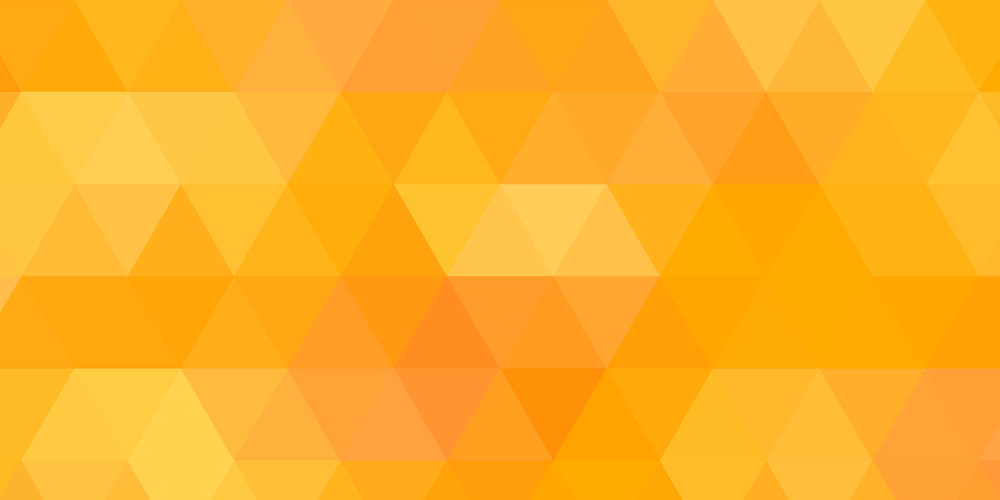花屋が知っておくべき葬儀マナー




はじめに
花屋の仕事は、ただ美しい花を販売することだけにとどまりません。特に葬儀の現場では、花が果たす役割は非常に大きく、適切なマナーや所作が求められます。花の選定から届け方、現場での立ち居振る舞いに至るまで、遺族の心に寄り添う姿勢が花屋に求められています。本記事では、花屋が知っておくべき葬儀マナーについて、実際の体験談や専門家の意見、公的機関からの情報を交えながら解説します。
葬儀と花屋の関係
葬儀における花の役割は、単なる装飾ではなく、故人への最後の贈り物であり、遺族や参列者の想いを可視化する大切な存在です。供花(きょうか)や枕花(まくらばな)、祭壇の装飾など、花屋が担う役割は多岐にわたります。
特に近年はオーダーメイド型の供花の需要が増え、遺族の想いを丁寧に聞き取り、それを花に込める提案力が花屋に求められています。感情を形にする花屋の姿勢は、今後ますます重視されていくでしょう。
供花の基本知識
供花の種類
- 枕花:通夜前に故人の枕元に供える花。白を基調にした控えめなデザインが多い。
- 祭壇供花:式場の祭壇に飾る花。地域や宗派によって配置のルールが異なる。
- 会場装花:式場全体の装飾に用いる。会場によって規定があるため事前確認が必要。
避けるべき花材と色
香りが強すぎる花やトゲのある花、派手な赤系統の花は避けましょう。宗教や地域性に応じた配慮が求められます。
「仏式葬儀では白や紫、青など落ち着いた色の花が推奨されます。赤い花や派手な花は避けるべきとされています。」
(公益社団法人 全日本冠婚葬祭互助協会)
葬儀会場での振る舞いマナー
搬入・設置時の注意
黒やダークカラーの目立たない服装を着用し、遺族や会場スタッフへの配慮を忘れないようにします。静かな声で必要最小限の会話にとどめ、作業音も最小限に抑えるように心がけましょう。
遺族との接し方
遺族と接する際は、無理に話しかけず、相手からの声掛けに対してのみ簡潔かつ丁寧に応じるのが基本です。葬儀社の進行や会場の都合に影響を与えないよう、撤収や再訪のタイミングも事前に確認しておくべきです。
現場から学ぶ実例
実例1:地方の文化に合わせた対応
「ある地方の葬儀では、白菊を中心とした構成が必須でした。地元葬儀社との事前調整により、無事納品でき、遺族から感謝の言葉をいただきました。」
(引用:note『フラワーデザイナーの葬儀現場日記』)
実例2:筆耕システムの導入で信頼向上
「以前は手書きで芳名板を作成していましたが、ミスが多く困っていました。筆耕ソフト『いちばん』を導入してからは、正確で見栄えも良くなり、葬儀社との信頼関係も強まりました。」
(フラワーショップA社/いちばんLP仕様書より)
専門家・公的機関の見解
「葬儀において供花は、哀悼と慰めの象徴です。その選定と届け方には細心の注意が必要です。」
(厚生労働省『葬儀の手引き』)
「花屋は単なる業者ではなく、葬儀における『ホスピタリティの一端』を担う存在です。」
(一般社団法人 日本葬送文化振興協会)
まとめ
花屋が葬儀の現場で求められるのは、花の美しさだけではありません。マナーや所作、配慮のある対応を通じて、遺族に安心感と信頼を与えることが大切です。また、筆耕ソフト「いちばん」や思い出パネルといったツールを活用すれば、効率的かつ心のこもった対応が可能になります。
今後、花屋が葬儀業界と連携しながらプロとして信頼されるためには、マナーと技術の両立が求められるでしょう。
よくある質問
-
供花を注文する際に必要な情報は?
-
故人の宗派、葬儀の日程、会場名、遺族の希望(花の種類・色など)を事前に確認しましょう。
-
名札の書き方で注意すべき点は?
-
名前や肩書の誤字脱字は厳禁です。筆耕システムなどを使って正確に仕上げることが大切です。
-
花屋として葬儀業界と長く関係を築くには?
-
丁寧なマナーと安定した品質、そして柔軟な対応力が鍵となります。信頼を積み重ねることが最も重要です。