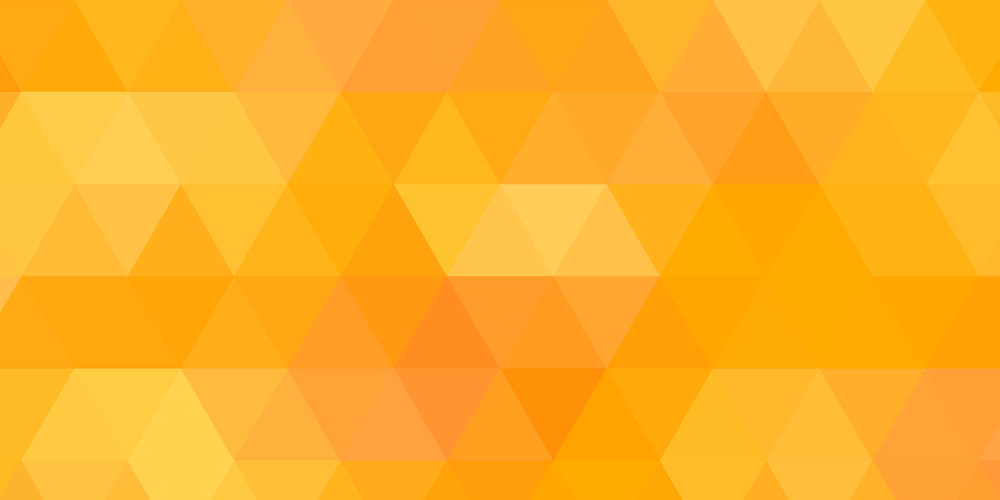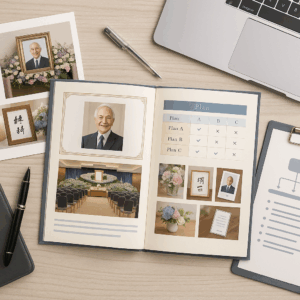花業界の基礎用語がこれでわかる!生花市場で使われる専門用語をやさしく解説

はじめに
生花市場には、「セリ」「買参人」「ロット」「バケツ」など、業界ならではの専門用語が飛び交っています。それらの意味をきちんと理解することが、取引の効率化や信頼関係の構築になります。本記事では、初心者にもすぐに役立つ基本用語を厳選し、シンプルかつ具体的に解説します。オンライン流通・業界団体の情報も織り交ぜ、わかりやすさと信頼性を両立させました。
生花市場とは?
生花市場とは、農家や輸入業者が出荷した花が、卸売業者や小売業者へと渡っていく流通の中枢です。日本にはおよそ40か所の公設卸売市場があり、切り花の流通量は2023年に約29億本に達しています。市場では「セリ(競り)」や「相対(あいたい)」を通じて取引が進みます。
また、全国には業界の取りまとめを行う一般社団法人日本花き卸売市場協会があり、流通の適正化や標準化に注力しています
生花市場で頻出!基本用語の解説
セリ(競り)
出荷された花を買参人が競い合って購入する形式で、主に「逆競り」(高い価格からスタートして徐々に下がる)が採用されています。
相対(あいたい)
事前に価格や数量を出荷者と交渉して決める個別取引。納期や支持品質を調整できるメリットがあります。
買参人(ばいさんにん)
競りに参加するための資格を持つ業者。市場ごとに登録申請・審査を受け、「買参証」が交付されます。
ロット
同一の品種や品質でまとめられた出荷単位。数量の目安として重要な分類です。
バケツ
花を水に浸し鮮度を保つための容器。市場では「バケツ〇本」で数量・価格の単位となります。
等級(グレード)
花の品質を評価する基準。茎の長さ、花つき、色調、傷の有無などで分類されます。
キャリー
市場内で花を運ぶ台車・カゴ車のこと。大量運搬に不可欠な道具です。
着色花
自然に白い花に、染料などを用いて人工的に色付けした商品。イベントやギフトで人気です。
オンライン流通でよく出る用語
フラワーオークション
オンライン上で行われる「競り」。遠隔地からでも参加でき、セリ落としが可能です。株式会社フラワーオークションジャパンが大田市場で展開しています。
出荷者コード・買参人コード
オンライン流通では、出荷者や買参人それぞれに固有のコードが割り振られ、商品管理・決済に使用されます。
これらのコードは、あらかじめ市場や取引先の卸売業者へ申請し、所定の手続きと審査を経て取得する必要があります。自動で発行されるものではありません。
たとえば買参人コードは、取引を希望する市場(例:大田市場など)で開業届や身分証、登録料などを提出して登録申請を行うと、仮証が発行され、のちに本登録となります。
出荷者コードも同様に、出荷契約を締結後に市場内の取引業者より付与される形式です。
市場ごとに必要書類や手順が異なるため、取引を希望する市場に事前に確認することが重要です。
用語がわかると業務が変わる!3つのメリット
- 取引がスムーズになる
「セリ」と「相対」の違いを把握すると、仕入れ手法を目的に応じて選べるようになります。 - 在庫・ロスを減らせる
「ロット」や「グレード」を意識すれば、適切な量と品質の仕入れが可能になり、無駄が減ります。 - 市場関係者との意思疎通が円滑に
業界用語を使いこなすことで「信頼できる相手」として認識され、交渉や連携がスムーズになります。
補足:流通の現場背景と業界団体の取り組み
- 価格・数量動向:農林水産省の資料によれば、国内花きの流通構造は国内生産が約9割、輸入が1割で、切り花が国内生産の6割を占めています。
- 業界標準化の取り組み:日本花き卸売市場協会は、物流効率化やオンライン取引の導入などを推進しています。
まとめ
今回ご紹介した専門用語――「セリ」「相対」「買参人」「ロット」「バケツ」「等級」「キャリー」「着色花」「フラワーオークション」、「コード」――を正しく理解すれば、生花市場の仕組みや取引ルールが明確になり、業務の精度や交渉力が格段にアップします。
辞書のように参照しながら、実際の市場やオンライン取引の現場でもぜひ使ってみてください。
よくある質問(Q&A)
-
生花市場は誰でも入れる?
-
一般入場は基本的に不可。見学したい場合は市場管理者に事前申込が必要です。
-
買参人証を取得するには?
-
市場ごとに申請・審査を受け、「買参証」が発行されます。手続きには数千円程度の費用と数週間~数か月の時間を要します。
-
オンライン取引は初心者にも使える?
-
はい。フラワーオークションの多くはオンライン参加が可能で、遠方の仕入れ先ともつながります。